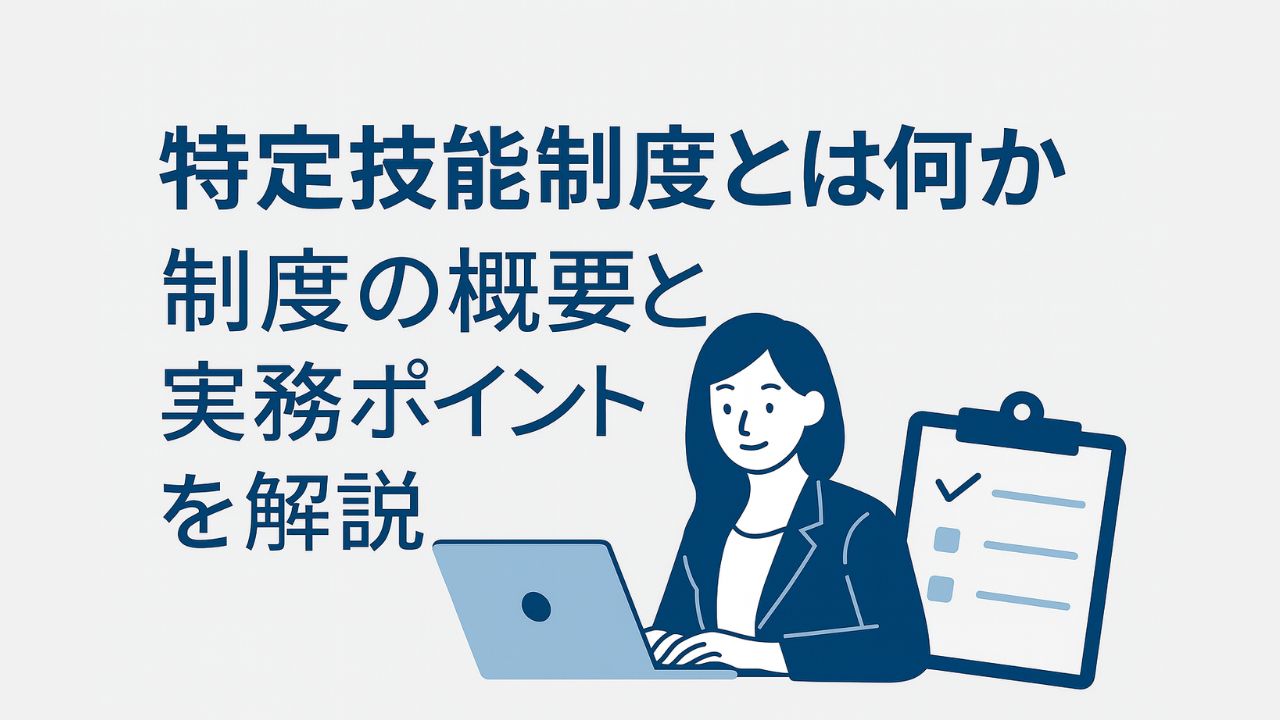【要点まとめ】
- 特定技能の全体像と実務手順を一気通貫で整理したガイド
- 収録内容:制度の仕組み/16分野一覧/費用相場/採用国比較/成功事例/FAQ/各種テンプレ
- 基本フロー:要件棚卸 → 分野選定 → 採用国比較 → 概算コスト → 支援体制整備 → 採用・手続 → 定着運用(3/30/90日面談)
- コスト試算は「採用・手続」「月次支援」「住居」「言語・通訳」「備品」に分解して比較
- 受入の前提:直接雇用・労働法遵守・安全衛生教育・多言語文書・相談窓口の整備
- 更新方針:告示・運用の改定に合わせて随時アップデート
目次
はじめに
あなたの会社で「外国人を雇いたい」と思ったとき、まず制度を正しく理解することが肝心です。「技能実習制度」と「特定技能制度」は名前が似ていて混同されがちですが、目的も要件も働き方も大きく違います。間違えると、法的なリスクが発生したり、コストや手続きで思わぬ負担を負うことになったりします。
このガイドでは、外国人雇用初心者の人事担当者の方が、「どちらの制度を使うか」「準備すべきことは何か」を判断できるように、制度の仕組み・メリット・デメリット・注意点を比較しながら解説します。
制度の目的の違い
| 制度 | 主な目的 |
|---|---|
| 技能実習制度 | 発展途上国等の外国人に「日本で技能・技術を習得して母国に帰って広めてもらう」こと。国際貢献、技術移転が軸。 |
| 特定技能制度 | 日本国内の人手不足を緩和すること。即戦力の外国人材を受け入れて、業務に従事してもらうことが目的。 |
主な比較ポイント
| 比較項目 | 技能実習制度 | 特定技能制度 |
|---|---|---|
| 在留資格 | 技能実習 | 特定技能 |
| 制度の目的 | 技能・技術を習得して母国に還元 | 日本の人手不足を補う即戦力人材の確保 |
| 在留期間 | 最長5年(1号→2号→3号の順で更新) | 特定技能1号:最長5年 特定技能2号:上限なし |
| 日本語・技能要件 | 基本的には要件なし(職種により一部試験あり) | 日本語試験+技能試験の合格が必要 |
| 転職可否 | 原則不可(同じ実習先でのみ継続) | 同一分野内なら転職可能 |
| 家族帯同 | 不可 | 1号:不可、2号:可能 |
| 手続き | 監理団体を通じて計画を作成し申請 | 企業または登録支援機関が直接申請 |
技能実習制度の特徴
- 海外の送り出し機関と契約し、監理団体を通じて受入れ
- 1号→2号→3号と段階的に技能を高める仕組み
- 実習内容や生活環境について厳格な監督がある
- コストは比較的抑えられるが、転職ができないためミスマッチ時は大きな負担
- 日本語力が低いケースも多く、指導に手間がかかる場合がある
特定技能制度の特徴
- 日本語試験・技能試験に合格した即戦力人材を採用可能
- 長期雇用を見据えられる(特定技能2号なら在留期間上限なし)
- 家族帯同が可能になり定着率が上がるケースもある
- 支援計画の作成、生活支援の実施など企業側の責任が重い
- 採用コストや人件費は技能実習より高めになる傾向
まとめ
- 「研修」「国際貢献」を重視し、コストを抑えて育成したいなら技能実習制度
- 「即戦力」「長期雇用」を重視し、安定した人材確保を狙うなら特定技能制度
- いずれの場合も、制度の要件や法令を守らないと罰則リスクがあるため、専門家や登録支援機関の活用が有効
よくある質問(FAQ)
Q. まず何から始めればいいですか?
A. 自社の要件(職種・勤務地・就業時間・日本語要件・受入人数・住環境)を棚卸しし、対象分野と採用国の候補を2〜3に絞るのが最短ルートです。本ガイドの「活用手順」に沿うと迷いにくくなります。
Q. 特定技能1号と2号の違いは?
A. 1号は即戦力レベルで在留は通算最長5年・家族帯同は原則不可。2号は熟練水準で更新上限なし・家族帯同可。2号へ移行できるかは分野によって異なります。
Q. 法人でなく個人事業主でも受入できますか?
A. 可能です。営業許可・直接雇用・労働法遵守・支援体制の確保などの前提を満たしていることが必要です。
Q. 必要な試験や日本語レベルは?
A. 原則として「技能試験」と「日本語試験」の合格が必要です(技能実習2号良好修了者などは一部免除あり)。日本語は日常会話レベル(N4目安)が多いですが、接客比重に応じて基準を上げる運用が現実的です。
Q. 受入れは派遣でも可能ですか?
A. 基本は受入企業による直接雇用です。派遣先就労は不可が原則なので、最新の運用・告示を必ず確認してください。
Q. 登録支援機関は必須ですか?
A. 自社で生活オリエンテーション、住居確保、日本語学習支援、相談窓口等を適切に実施できれば必須ではありません。不安がある場合は登録支援機関の活用が現実的です。
Q. 概算コストはどのように見積もれば良い?
A. 費用を「採用・手続」「月次支援」「住居関連」「日本語・通訳」「備品」の5カテゴリに分解し、内製/外部化で見積ります。ガイド内の試算テンプレを利用すると比較が容易です。
Q. 受入人数の上限はありますか?
A. 一律の人数上限はありませんが、教育・指揮監督・安全衛生・労務管理の体制に見合わない受入は不許可・更新不許可のリスクが高まります。段階導入が安全です。
Q. 家族帯同は可能ですか?
A. 1号は原則不可、2号は配偶者・子の帯同が可能です。2号へ移行できるかは分野別運用に依存します。
Q. 離職・転職・途中帰国が起きた場合の対応は?
A. 所管庁への届出、未払い清算、住居・ライフラインの整理支援、記録書類の整備が必要です。日常的に就業・支援記録を残すことがトラブル抑止になります。
Q. 多言語対応はどこまで必要?
A. 就業規則・安全衛生・ハラスメント方針・シフト連絡などの重要文書は多言語で整備し、口頭指示ではなく文書・掲示・研修で反復周知する設計が有効です。
Q. 面談や教育はどの頻度で実施すべき?
A. 入社後の3日・30日・90日で定点面談を推奨。以降は四半期ごとに評価・安全衛生・日本語学習の進捗を確認します。
Q. 採用国の選び方は?
A. 言語・文化・生活立ち上げ難易度・候補者層の厚み・相場費用を比較し、自社業務との相性で選定します。複数国の少人数パイロット導入も有効です。
Q. 情報はどの程度アップデートされますか?
A. 告示・運用の改定に合わせて随時更新します。各記事の更新日とお知らせ欄で最新状態を確認できます。
Q. 個別の相談は可能ですか?
A. 可能です。ページ下部の問い合わせフォームから「分野・地域・想定人数・導入時期」を添えてご連絡ください。初回ヒアリング用のチェックリストを返信します。